晶苑の篆刻と書
愛媛大学教育学部准教授 東 賢司
はじめに
晶苑が本格的に篆刻を始めたのは、昭和21年に松丸東魚主催の「知丈印社」に入門してからである。以後平成12年になくなるまでの55年間、篆刻作品を作り続けている。晶苑が篆刻を始めた頃に、女性で篆刻家となっていた者はおらず、女流篆刻家第一号といっても過言ではなかろう。晶苑は日展・毎日展を中心にして活動を行っていたが、女流篆刻家としての歩みは簡単なものではなかった。別に取り上げている「えひめ人その風土」の中でも、「会うなり、『女子供のする仕事じゃない。帰れ、帰れ』と、こうなんですよね」と語っているように、東魚の弟子になるだけでも、大変な苦労をしている。確かに篆刻という芸術活動は、書 作活動の中でも、最も体力・腕力を必要とする。刃渡り一セ ンチほどの小さな鉄筆(印刀)で、おおきいものだと10センチ角の大きさの石に細かく文字を彫りつけるのである。その作業の大変さは、篆刻を経験したもの皆が経験している。また、篆刻は大変目の神経を使う活動でもある。細かい作業の連続であるので、集中力のある人にしか続けることは出来ない。晶苑の篆刻の時間は夜中が中心だったようである。東京青山の自宅には、八畳ほどの
作活動の中でも、最も体力・腕力を必要とする。刃渡り一セ ンチほどの小さな鉄筆(印刀)で、おおきいものだと10センチ角の大きさの石に細かく文字を彫りつけるのである。その作業の大変さは、篆刻を経験したもの皆が経験している。また、篆刻は大変目の神経を使う活動でもある。細かい作業の連続であるので、集中力のある人にしか続けることは出来ない。晶苑の篆刻の時間は夜中が中心だったようである。東京青山の自宅には、八畳ほどの 篆刻専用の和室(百壺斎)があり、そこで多くの名作が作成された。部屋には印譜などがうず高く積まれ、学書の跡を偲ぶことができる。後に紹介することになるが、非常に手先が器用であり、篆刻に必要なほとんどのものは、自ら作製することができた。晶苑の遺品を見ると、手製の文房が数多く残されている。その中で最も注目したいのは、『晶苑自鈐印譜』(全14冊)、『晶苑印艸』(全14冊)、『晶苑印艸』『晶苑印存』(各1冊)がある。これらは、印箋の印刷、押印は晶苑の自作であり、製本は宮内庁書陵部に依頼していた。
篆刻専用の和室(百壺斎)があり、そこで多くの名作が作成された。部屋には印譜などがうず高く積まれ、学書の跡を偲ぶことができる。後に紹介することになるが、非常に手先が器用であり、篆刻に必要なほとんどのものは、自ら作製することができた。晶苑の遺品を見ると、手製の文房が数多く残されている。その中で最も注目したいのは、『晶苑自鈐印譜』(全14冊)、『晶苑印艸』(全14冊)、『晶苑印艸』『晶苑印存』(各1冊)がある。これらは、印箋の印刷、押印は晶苑の自作であり、製本は宮内庁書陵部に依頼していた。
では、晶苑の篆刻作品を解読してゆくことにする。晶苑の篆刻家としての歩みを三期に分けて鑑賞してみたい。
Ⅰ 篆刻 第一期 師風の継承(昭和27年~昭和50年)
この時期は、師匠松丸東魚に師事してから、東魚が死亡するまでの34年間である。
知
 丈印社に入社したのが、昭和21年(23歳)であるが、確認できる作品で最も古いのは、昭和27年(29歳)の第八回日展の初入選作「朝木蘭飲墜露夕秋菊響落英」(白文)である。その前年の昭和26年(28歳)のときに、第三回毎日展に出品し、最高賞(毎日賞)を受賞しているが、残念ながらその作品は確認できない。師の東魚は、その前年の第二回展から出品しているので、相当に若い時期からの出品である。この時期は、東魚に師事して8年になるが、ひたすら模刻を行っていたことが想像できる。
丈印社に入社したのが、昭和21年(23歳)であるが、確認できる作品で最も古いのは、昭和27年(29歳)の第八回日展の初入選作「朝木蘭飲墜露夕秋菊響落英」(白文)である。その前年の昭和26年(28歳)のときに、第三回毎日展に出品し、最高賞(毎日賞)を受賞しているが、残念ながらその作品は確認できない。師の東魚は、その前年の第二回展から出品しているので、相当に若い時期からの出品である。この時期は、東魚に師事して8年になるが、ひたすら模刻を行っていたことが想像できる。
この作風は、30歳後半まで続いている。昭和34年(36歳)の第二回日展入選作「耿湋詩 秋日」(白文)では、「秋返則人閭恭…」という二十文字を四行で刻している。この作品は、1文字目の「秋」という文字が4行目の最後に刻されている。篆刻の技法では「回文」と言う。このような工夫をしながら製作をしているが、文字そのものは、漢印の影響を受けている。師の東魚が、漢印の模刻を指導の基本にしていたことは有名であるが、晶苑も師の教えを忠実にまもっていたことが分かる。
この後、晶苑の書作は順調である。
 日展には、第二回から第五回まで連続入選している。また、昭和35年(37歳)の 第十二回毎日展では「道里悠長」「聴所未聞」(2顆とも白文)で委嘱となっている。さらに、昭和37年(39歳)の第十四回毎日展では「復何疑」(朱文)「窮至骨」(白文)で毎日準大賞を受賞し、毎日展会員となっている。これらの作品は、
日展には、第二回から第五回まで連続入選している。また、昭和35年(37歳)の 第十二回毎日展では「道里悠長」「聴所未聞」(2顆とも白文)で委嘱となっている。さらに、昭和37年(39歳)の第十四回毎日展では「復何疑」(朱文)「窮至骨」(白文)で毎日準大賞を受賞し、毎日展会員となっている。これらの作品は、 非常に勢いのあ
非常に勢いのあ る刻線をしており、初期作品の代表作と言うことができる。日展にしても、毎日展にしても、他の分野に対して篆刻の出品数は少ないので、驚くべき受賞歴である。
る刻線をしており、初期作品の代表作と言うことができる。日展にしても、毎日展にしても、他の分野に対して篆刻の出品数は少ないので、驚くべき受賞歴である。
これらの作例は、漢印風というよりも、むしろ展覧会で目立つ作風となっている。昭和36年(38歳)の第四回に出品した
 「虚空低頭」(朱文)は、今までには見られない作例である。ところが、師の東魚の作品を調べてみると、「行行失故路」等は、この書風と共通点している。当時の師風・書壇の流行があったのかもしれないが、様々な作例を確認できる最も特徴的な時期である。
「虚空低頭」(朱文)は、今までには見られない作例である。ところが、師の東魚の作品を調べてみると、「行行失故路」等は、この書風と共通点している。当時の師風・書壇の流行があったのかもしれないが、様々な作例を確認できる最も特徴的な時期である。
この後一時期スランプを迎える。昭和38年(40歳)に銀座内科院長で医師の藤井尚治と結婚する。藤井は、今では誰もが口にする「ストレス」には早くから着目し、「ストレス学説」の提唱者ハンス・セリエ博士と親交を結んでいる。セリエ博士の来日に尽力し、自ら私費を投じて設立した財団法人「東京ストレス研究会」の理事長として、日本のストレス研究と紹介に大きな業績を残した人物である。
私的には大変幸せな時期であったが、『知丈通信』第三十号(昭和38年9月20日)の「夏期錬成会終わる」のコーナーで、「河野女史は一寸スランプ気味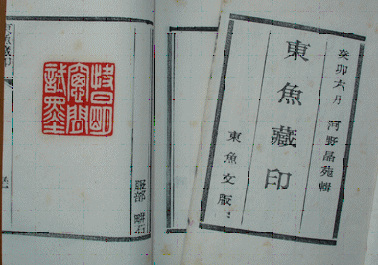 と見受けた。一番苦しんでいる様子、勉強の合間合間に出来ない我々のための用事で馳せ回るので落ち着かれないのではなかろうか。我々の感謝の的ではあるが、御主人におかれては本当に大変なことだろうと拝察する」と記載されている。
と見受けた。一番苦しんでいる様子、勉強の合間合間に出来ない我々のための用事で馳せ回るので落ち着かれないのではなかろうか。我々の感謝の的ではあるが、御主人におかれては本当に大変なことだろうと拝察する」と記載されている。
この年は、後に紹介する『東魚蔵印』の作製に心血を注いでいたので、作品に十分集中できなかったのではないかと推測している。
その後、日展には当落を繰り返すが、昭和43年(45歳)の第二十回毎日展では初の審査員となり、「推胡蘆」(朱文)を出品している。また、同年の第十一回日展では「蟻潰堤」(朱文)を出品、入選を果たしている。この年からは、知丈印集の編集担当になっている。毎日展の審査
 員は翌年の昭和44年(46歳)の時も務め、日展では、この年から8年連続で入選している。
員は翌年の昭和44年(46歳)の時も務め、日展では、この年から8年連続で入選している。
昭和45年(47歳)の時に毎日系の女性作家の書道作品を一堂に展示する「第一回現代女流書展」が日本橋高島屋で開催される。ここには「箭既離」(朱文)を出品している。篆刻出品は、晶苑だけであり、ここからも女性篆刻家が少ないことが確認できる。
 一時のスランプを脱した晶苑は、傑作を連発する。昭和47年(49歳)の第二十四回毎日展では、3度目の審査員を務め「虚玄大道」(朱文)を出品、同年の第四回日展には「鐵槌撃砕黄金骨」(朱文)を出品している。
一時のスランプを脱した晶苑は、傑作を連発する。昭和47年(49歳)の第二十四回毎日展では、3度目の審査員を務め「虚玄大道」(朱文)を出品、同年の第四回日展には「鐵槌撃砕黄金骨」(朱文)を出品している。
昭和48年(

 50歳)には東魚の主導で『昭和蘭亭印集』を作製し、蘭亭序の文末区「亦將有感於斯文」が掲載されている。12月には全日本書道連盟の評議員となり、篆刻家としての地位が不動のものとなっている。
50歳)には東魚の主導で『昭和蘭亭印集』を作製し、蘭亭序の文末区「亦將有感於斯文」が掲載されている。12月には全日本書道連盟の評議員となり、篆刻家としての地位が不動のものとなっている。
昭和50年(52歳)6月9日に師匠の東魚が死去、この後は、一人で作品製作を行ってゆくことになる。
第二期 自己書風の模索(昭和51年~昭和64年)
師匠東魚との死別により、独り立ちを余儀なくされる。この14年間は、東魚との決別・自己の書風を確立しようと模索する時期である。
知丈印社がいつまで続いたのか定かでないが、『知丈通信』のファイルは第五十号(昭和50年)までしか発行されていない。また、昭和51年以降の資料を整理してみると、印社の活動は自然消滅していたようである。晶苑の働きかけにより、知丈印社の筆頭であった吉野松石が動き、昭和56年8月29日に銀座キャピタルホテルにて印社再興のための会議が招集される。吉野松石に委託された晶苑が会議の段取りや資料作成を行っている。ここでの議論の中心は、印社規約を作成することにあった。翌年の昭和57年7月21日には、ライオン銀座7丁目店で総会を開催し、「知丈印社会則」「知丈印社運営細則」が決定されている。会則の第二条には「知丈印社は、その創立者松丸東魚の遺志を継ぎ、篆刻の研究を通じてその発展向上につとめることを目的とし、同人・会員及びその趣旨に賛同するものをもって構成する」とある。東魚存命のときから既に、社員が社中をもっていたので、体勢を見直して現状にある組織作りを目指したようである。
その後、代表になった吉野松石が「印社再編にあたって」の一文を、同時に「役員の指名」として、吉野が指名する役員が列挙されている。晶苑は運営委員・事務長・会計を担当することになり、早速事務連絡を行っている。それによると、印社総勢が170人になっていることが分かる。また、後にあげる全日本篆刻連盟役員展でおなじみの別名、「藤晶苑」もこれが初出である。本人いわく「私用との区別の為」である。知丈印社再興へのなみなみならぬ意欲を感じることができる。
さて、この時期の作品についてであるが、第一期と比較して大きな違いが見られる。日展についてであるが、大半
 の出品が落選となる。入選したのは、昭和51年(53歳)の第八回日展出品作の「孤燈成華」(白文)と昭和62年(64歳)の第十九回日展出品作の「風知草彊」(朱文)のみである。昭和52年から8回連続して落選したあとの昭和60年(62歳)には、日展篆刻作家展が開催される。当時の日展の篆刻作家は、評議員4名、会員4名、委嘱3名、会友12名という小所帯であり、会友の協力を得ないで展覧会を開催することは出来なかったと思われる。当時会友になっていた晶苑は「指鹿為馬」(白文)
の出品が落選となる。入選したのは、昭和51年(53歳)の第八回日展出品作の「孤燈成華」(白文)と昭和62年(64歳)の第十九回日展出品作の「風知草彊」(朱文)のみである。昭和52年から8回連続して落選したあとの昭和60年(62歳)には、日展篆刻作家展が開催される。当時の日展の篆刻作家は、評議員4名、会員4名、委嘱3名、会友12名という小所帯であり、会友の協力を得ないで展覧会を開催することは出来なかったと思われる。当時会友になっていた晶苑は「指鹿為馬」(白文) という興味深い作品を出品している。この言葉は「是非を転倒する」という中国の故事成語であるが、このころの日展の運営を暗に非難した作と考えることができる。
という興味深い作品を出品している。この言葉は「是非を転倒する」という中国の故事成語であるが、このころの日展の運営を暗に非難した作と考えることができる。
また、毎日展においては、この間四度の審査員となっている。その4回の作品をあげてみる。
昭和51年(53歳)第二十八回展「何有遠之」(朱文)
昭和52年(54歳)第二十九回展「物外情楽」(白文)
昭和55年(57歳)第三十二回展「挿明鏡」(朱文)
昭和59年(61歳)第三十六回展「不言以匪愁」(朱文)
これらの作は、すべて書風が異なる実験作ということができるが、いずれも師風を脱して自己の書風を確立する経過の時期、と考えることができる。







昭和63年(65歳)の時には、中国杭州市西泠印社で開催の、「記念西泠印社建社八十五周年国際篆刻書画展覧」に作品を出品している。その図録には「山近雲多態」を出品したようであるが、実際には「與時倶化」「弾枝頭残雪」「雨余蛙鳴鼓」の合計4作を用意したようであり、晶苑の意気込みをうかがうことができる。
第三期 自己書風の展開(平成元年~平成11年)
この11年間は、独自の書風が確立し、作製に自信を深めている時期と言える。
毎日展には出品せず、日展には出品 しているものの、入選はわずか一度である。
しているものの、入選はわずか一度である。
 平成10年(75歳)の第三十回日展に久しぶりに入選した「天雨粟鬼夜哭」(朱文)「胡蝶嘆秋」(朱文)の2作は、まさに晶苑芸術の結晶ということができる。
晶苑の作家としての出品の場は、日本篆刻会展(後に全日本篆刻連盟役員展)に広がっている。平成2年(67歳)のときに、日本篆刻連盟の評議員となり、以後平成11年まで毎年出品している。平成2年に日本篆刻会展に出品したのは「往燕来鴈」である。洗練された刻線が印面を支配しており、実にすがすがしい印象を持つ。
平成10年(75歳)の第三十回日展に久しぶりに入選した「天雨粟鬼夜哭」(朱文)「胡蝶嘆秋」(朱文)の2作は、まさに晶苑芸術の結晶ということができる。
晶苑の作家としての出品の場は、日本篆刻会展(後に全日本篆刻連盟役員展)に広がっている。平成2年(67歳)のときに、日本篆刻連盟の評議員となり、以後平成11年まで毎年出品している。平成2年に日本篆刻会展に出品したのは「往燕来鴈」である。洗練された刻線が印面を支配しており、実にすがすがしい印象を持つ。 全日
全日 本篆刻連盟と関連して、三期には中国での作品展に3度出品している。
本篆刻連盟と関連して、三期には中国での作品展に3度出品している。
その作品を紹介してみよう。
平成6年(71歳)全日本篆 刻連盟篆刻芸術展・北京展
・「大智據悲」(白文)
・「蝉不知雪」(朱文)

 ・「易徳無価宝」(朱文)
・「易徳無価宝」(朱文)
・「壮志飛翔」(朱文)
・「聴謦咳」(朱文)
これらの作品には「蝉不知雪」「聴謦咳」にように、晶苑が生涯何作も作製した題材を確認することができる。造形的にもおもしろく、晩年の充実した作である。
平成8年(73歳)九六日中篆刻家作品交流展 
・「籬華残」(朱文)
・「弦月滴夜霧」(朱文)
・「虚空在道標」(朱文)
・「博望侯印」(朱文)
平成10年(75歳)全日本篆刻連盟篆刻芸術展・上海展
・「壮士不還」(朱文)
・「煙雨囁季」(朱文)
・「遠鴎浮静」(白文)
・「気成虹」(未確認)
これらの作品では、晶苑書風が遺憾なく発揮されている。その中でまた新たな作風作りを目指している姿勢もう
 かがわれる。「博望侯印」は、封泥の模刻のような印風をしている。晶苑のメモによると、中国の前漢時代の「張騫」が、大将軍衛青率いる匈奴への遠征で大勝利を得た時に与えられた官職名が「博望侯」であることが分かる。これと同じ題材の印は平成7年(72歳)の第五回全日本篆刻連盟役員展にも出品されていて、晶苑のこだわりを再確認することができる。
かがわれる。「博望侯印」は、封泥の模刻のような印風をしている。晶苑のメモによると、中国の前漢時代の「張騫」が、大将軍衛青率いる匈奴への遠征で大勝利を得た時に与えられた官職名が「博望侯」であることが分かる。これと同じ題材の印は平成7年(72歳)の第五回全日本篆刻連盟役員展にも出品されていて、晶苑のこだわりを再確認することができる。
晶苑の絶筆は晩年、多くの模刻を行っている。確認出来る資料だけで約130顆である。これらの作例の順番ははっきりしない。
模刻は、主として古璽(漢代以前の印)が中心である。晶苑の手元にあった陳介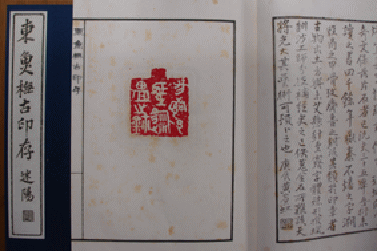 祺編『十鐘山房印挙』等が使用されているが、その精密さは度肝を抜かれる。七十を過ぎた老人がここまで細かい仕事が出来るということは、晶苑が持って生まれた器用さを証明している。
祺編『十鐘山房印挙』等が使用されているが、その精密さは度肝を抜かれる。七十を過ぎた老人がここまで細かい仕事が出来るということは、晶苑が持って生まれた器用さを証明している。
最晩年に模刻を行ったことについて「ある人物から古印の勉強をされたらどうかと勧められた」と、周辺の人に漏らしている。しかし、師の東魚の最後の仕事が『東魚撫古印存』(東魚の模刻集)を刊行することであった事を知っていた晶苑は、師を追って模刻集を作ることを目指していたのではないだろうか。実際、模刻をするための布字が多く残されている。
Ⅱ 木額と書
木額については、作品数が少ない。その中での代表作は、「晶苑」と書いた木額である。この木額には「東魚長」と彫られているので、一見師匠の松丸東魚の作のように見える。ところが、左下を見ると、小さな篆書で「晶苑所刻」と刻され、晶苑が鑿を持って作製した
 ことが確認できる。おそらく東魚が存命中に木額の下書きを行い、それを晶苑が刻したと思われる。晶苑という雅号は、昭和27年の『知丈通信』に見られるので、昭和
ことが確認できる。おそらく東魚が存命中に木額の下書きを行い、それを晶苑が刻したと思われる。晶苑という雅号は、昭和27年の『知丈通信』に見られるので、昭和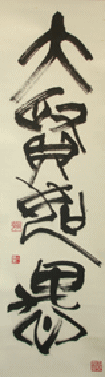 21年に入社しての比較的早期に東魚から頂き、木額作製も昭和20年代あたりの比較的早期の作と予想できる。非常に伸びやかな書風である。
21年に入社しての比較的早期に東魚から頂き、木額作製も昭和20年代あたりの比較的早期の作と予想できる。非常に伸びやかな書風である。
また「蝸廬」と書かれた木額は、「乙卯大呂」とあることから、昭和50年(52歳)の時に作製されたことがわかる。「蝸廬」の意味は「蝸牛のような丸い屋根の家。また、狭い家。」のことを意味する。
また、晶苑の書作であるが、これも残される作品は篆刻以外の肉筆書は非常に少ない。これらの作も先の「蝸廬」と同じく、茶席で使用されたものと思われる。これらの中にも、晶苑の篆刻に通じる作品がある。「大賢如愚」は日展の作品であるが、篆書の造形がすばらしい。篆刻家ならではの作品と言うことができる。
おわりに
晶苑の篆刻と書の特徴は、何かと問われると、白と赤あるいは白と黒のコントラストの見事さをあげることができる。晶苑の尋常ならぬ器用さがこの書風を作り出していることは間違いないが、作品に主として使用する書体は、「篆書」である。紹介してきた作品でも、篆書を自由自在に使いこなしていることを知ることができるが、篆書を自在に操るには当然、古代の文字に対する知識が必要になってくる。
晶苑は昭和50年代に東京都文京区湯島にある湯島聖堂の「聖社詩会」に通っていた。斯文会と言われる会が運営に当たっていたが、この講座を担当していたのが、当時東京大学を退職し二松学舎大学に勤務していた赤塚忠である。赤塚は当時日本人の中国古代研究者の第一人者であったが、市中の人にもわかりやすく古代文学を解説していた。その中には、文字学がふんだんに盛り込まれていたことが、晶苑のノートからも想像できる。これらの勉学を通じて、金文・篆書などの正確な文字構造や文字の原義を学んでいたことが分かる。
近年の流れとして篆刻だけではなく、書作品においても、篆書などの古代の文字を使用した作品を多く見かける。ただ、これらの作品には、造形のおもしろさや印象深さばかりをねらって、文字構造を変えてしまっているものがある。一方、晶苑の作品は、当時の流行を追うばかりではなく、馬鹿正直なまでに、文字学に忠実になっている。晶苑は晩年「作品作りが楽になった」と語っているが、実際、作風の広がりが確認できるものの、奇趣をねらった作品はない。この点でも、地に足をつけて地道な仕事を生涯通した、そういう篆刻家であった。
作活動の中でも、最も体力・腕力を必要とする。刃渡り一セ ンチほどの小さな鉄筆(印刀)で、おおきいものだと10センチ角の大きさの石に細かく文字を彫りつけるのである。その作業の大変さは、篆刻を経験したもの皆が経験している。また、篆刻は大変目の神経を使う活動でもある。細かい作業の連続であるので、集中力のある人にしか続けることは出来ない。晶苑の篆刻の時間は夜中が中心だったようである。東京青山の自宅には、八畳ほどの
篆刻専用の和室(百壺斎)があり、そこで多くの名作が作成された。部屋には印譜などがうず高く積まれ、学書の跡を偲ぶことができる。後に紹介することになるが、非常に手先が器用であり、篆刻に必要なほとんどのものは、自ら作製することができた。晶苑の遺品を見ると、手製の文房が数多く残されている。その中で最も注目したいのは、『晶苑自鈐印譜』(全14冊)、『晶苑印艸』(全14冊)、『晶苑印艸』『晶苑印存』(各1冊)がある。これらは、印箋の印刷、押印は晶苑の自作であり、製本は宮内庁書陵部に依頼していた。


 丈印社に入社したのが、昭和21年(23歳)であるが、確認できる作品で最も古いのは、昭和27年(29歳)の第八回日展の初入選作「朝木蘭飲墜露夕秋菊響落英」(白文)である。その前年の昭和26年(28歳)のときに、第三回毎日展に出品し、最高賞(毎日賞)を受賞しているが、残念ながらその作品は確認できない。師の東魚は、その前年の第二回展から出品しているので、相当に若い時期からの出品である。この時期は、東魚に師事して8年になるが、ひたすら模刻を行っていたことが想像できる。
丈印社に入社したのが、昭和21年(23歳)であるが、確認できる作品で最も古いのは、昭和27年(29歳)の第八回日展の初入選作「朝木蘭飲墜露夕秋菊響落英」(白文)である。その前年の昭和26年(28歳)のときに、第三回毎日展に出品し、最高賞(毎日賞)を受賞しているが、残念ながらその作品は確認できない。師の東魚は、その前年の第二回展から出品しているので、相当に若い時期からの出品である。この時期は、東魚に師事して8年になるが、ひたすら模刻を行っていたことが想像できる。
 日展には、第二回から第五回まで連続入選している。また、昭和35年(37歳)の 第十二回毎日展では「道里悠長」「聴所未聞」(2顆とも白文)で委嘱となっている。さらに、昭和37年(39歳)の第十四回毎日展では「復何疑」(朱文)「窮至骨」(白文)で毎日準大賞を受賞し、毎日展会員となっている。これらの作品は、
日展には、第二回から第五回まで連続入選している。また、昭和35年(37歳)の 第十二回毎日展では「道里悠長」「聴所未聞」(2顆とも白文)で委嘱となっている。さらに、昭和37年(39歳)の第十四回毎日展では「復何疑」(朱文)「窮至骨」(白文)で毎日準大賞を受賞し、毎日展会員となっている。これらの作品は、 非常に勢いのあ
非常に勢いのあ る刻線をしており、初期作品の代表作と言うことができる。日展にしても、毎日展にしても、他の分野に対して篆刻の出品数は少ないので、驚くべき受賞歴である。
る刻線をしており、初期作品の代表作と言うことができる。日展にしても、毎日展にしても、他の分野に対して篆刻の出品数は少ないので、驚くべき受賞歴である。

 「虚空低頭」(朱文)は、今までには見られない作例である。ところが、師の東魚の作品を調べてみると、「行行失故路」等は、この書風と共通点している。当時の師風・書壇の流行があったのかもしれないが、様々な作例を確認できる最も特徴的な時期である。
「虚空低頭」(朱文)は、今までには見られない作例である。ところが、師の東魚の作品を調べてみると、「行行失故路」等は、この書風と共通点している。当時の師風・書壇の流行があったのかもしれないが、様々な作例を確認できる最も特徴的な時期である。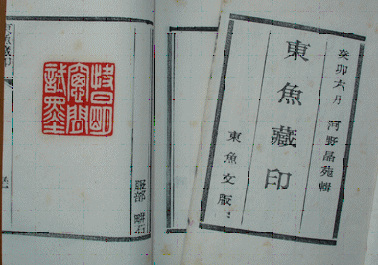 と見受けた。一番苦しんでいる様子、勉強の合間合間に出来ない我々のための用事で馳せ回るので落ち着かれないのではなかろうか。我々の感謝の的ではあるが、御主人におかれては本当に大変なことだろうと拝察する」と記載されている。
と見受けた。一番苦しんでいる様子、勉強の合間合間に出来ない我々のための用事で馳せ回るので落ち着かれないのではなかろうか。我々の感謝の的ではあるが、御主人におかれては本当に大変なことだろうと拝察する」と記載されている。
 員は翌年の昭和44年(46歳)の時も務め、日展では、この年から8年連続で入選している。
員は翌年の昭和44年(46歳)の時も務め、日展では、この年から8年連続で入選している。 一時のスランプを脱した晶苑は、傑作を連発する。昭和47年(49歳)の第二十四回毎日展では、3度目の審査員を務め「虚玄大道」(朱文)を出品、同年の第四回日展には「鐵槌撃砕黄金骨」(朱文)を出品している。
一時のスランプを脱した晶苑は、傑作を連発する。昭和47年(49歳)の第二十四回毎日展では、3度目の審査員を務め「虚玄大道」(朱文)を出品、同年の第四回日展には「鐵槌撃砕黄金骨」(朱文)を出品している。

 の出品が落選となる。入選したのは、昭和51年(53歳)の第八回日展出品作の「孤燈成華」(白文)と昭和62年(64歳)の第十九回日展出品作の「風知草彊」(朱文)のみである。昭和52年から8回連続して落選したあとの昭和60年(62歳)には、日展篆刻作家展が開催される。当時の日展の篆刻作家は、評議員4名、会員4名、委嘱3名、会友12名という小所帯であり、会友の協力を得ないで展覧会を開催することは出来なかったと思われる。当時会友になっていた晶苑は「指鹿為馬」(白文)
の出品が落選となる。入選したのは、昭和51年(53歳)の第八回日展出品作の「孤燈成華」(白文)と昭和62年(64歳)の第十九回日展出品作の「風知草彊」(朱文)のみである。昭和52年から8回連続して落選したあとの昭和60年(62歳)には、日展篆刻作家展が開催される。当時の日展の篆刻作家は、評議員4名、会員4名、委嘱3名、会友12名という小所帯であり、会友の協力を得ないで展覧会を開催することは出来なかったと思われる。当時会友になっていた晶苑は「指鹿為馬」(白文) という興味深い作品を出品している。この言葉は「是非を転倒する」という中国の故事成語であるが、このころの日展の運営を暗に非難した作と考えることができる。
という興味深い作品を出品している。この言葉は「是非を転倒する」という中国の故事成語であるが、このころの日展の運営を暗に非難した作と考えることができる。







 しているものの、入選はわずか一度である。
しているものの、入選はわずか一度である。
 平成10年(75歳)の第三十回日展に久しぶりに入選した「天雨粟鬼夜哭」(朱文)「胡蝶嘆秋」(朱文)の2作は、まさに晶苑芸術の結晶ということができる。
晶苑の作家としての出品の場は、日本篆刻会展(後に全日本篆刻連盟役員展)に広がっている。平成2年(67歳)のときに、日本篆刻連盟の評議員となり、以後平成11年まで毎年出品している。平成2年に日本篆刻会展に出品したのは「往燕来鴈」である。洗練された刻線が印面を支配しており、実にすがすがしい印象を持つ。
平成10年(75歳)の第三十回日展に久しぶりに入選した「天雨粟鬼夜哭」(朱文)「胡蝶嘆秋」(朱文)の2作は、まさに晶苑芸術の結晶ということができる。
晶苑の作家としての出品の場は、日本篆刻会展(後に全日本篆刻連盟役員展)に広がっている。平成2年(67歳)のときに、日本篆刻連盟の評議員となり、以後平成11年まで毎年出品している。平成2年に日本篆刻会展に出品したのは「往燕来鴈」である。洗練された刻線が印面を支配しており、実にすがすがしい印象を持つ。 全日
全日 本篆刻連盟と関連して、三期には中国での作品展に3度出品している。
本篆刻連盟と関連して、三期には中国での作品展に3度出品している。
 ・「易徳無価宝」(朱文)
・「易徳無価宝」(朱文)

 かがわれる。「博望侯印」は、封泥の模刻のような印風をしている。晶苑のメモによると、中国の前漢時代の「張騫」が、大将軍衛青率いる匈奴への遠征で大勝利を得た時に与えられた官職名が「博望侯」であることが分かる。これと同じ題材の印は平成7年(72歳)の第五回全日本篆刻連盟役員展にも出品されていて、晶苑のこだわりを再確認することができる。
かがわれる。「博望侯印」は、封泥の模刻のような印風をしている。晶苑のメモによると、中国の前漢時代の「張騫」が、大将軍衛青率いる匈奴への遠征で大勝利を得た時に与えられた官職名が「博望侯」であることが分かる。これと同じ題材の印は平成7年(72歳)の第五回全日本篆刻連盟役員展にも出品されていて、晶苑のこだわりを再確認することができる。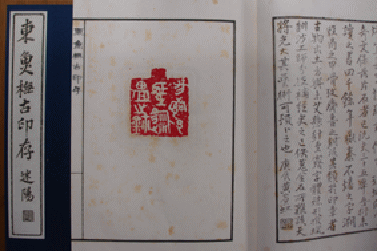 祺編『十鐘山房印挙』等が使用されているが、その精密さは度肝を抜かれる。七十を過ぎた老人がここまで細かい仕事が出来るということは、晶苑が持って生まれた器用さを証明している。
祺編『十鐘山房印挙』等が使用されているが、その精密さは度肝を抜かれる。七十を過ぎた老人がここまで細かい仕事が出来るということは、晶苑が持って生まれた器用さを証明している。
 ことが確認できる。おそらく東魚が存命中に木額の下書きを行い、それを晶苑が刻したと思われる。晶苑という雅号は、昭和27年の『知丈通信』に見られるので、昭和
ことが確認できる。おそらく東魚が存命中に木額の下書きを行い、それを晶苑が刻したと思われる。晶苑という雅号は、昭和27年の『知丈通信』に見られるので、昭和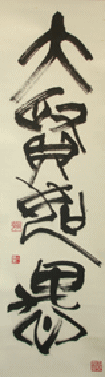 21年に入社しての比較的早期に東魚から頂き、木額作製も昭和20年代あたりの比較的早期の作と予想できる。非常に伸びやかな書風である。
21年に入社しての比較的早期に東魚から頂き、木額作製も昭和20年代あたりの比較的早期の作と予想できる。非常に伸びやかな書風である。